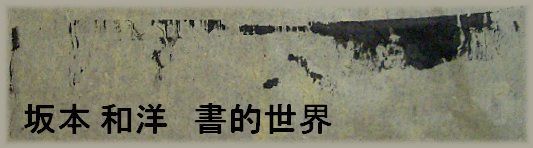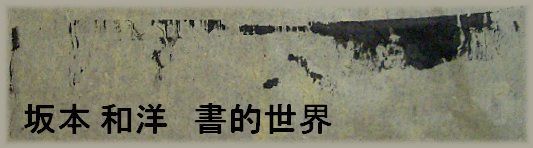|
作品制作コンセプト一新後の第100作を記念し、また本HP開設から20年の節目を迎えるにあたり、「ご挨拶」を改めました。
時代の変遷とともに、創作を取り巻く環境は大きく変わりました。
創字を始めた1996年当時、インターネットはまだ発展途上であり、検索エンジンで調べるという発想すら一般的ではありませんでした。情報取得の方法が、今となっては知る人が少ないTelnet等からブラウザへと移行し、MosaicからNetscape Navigator、そしてInternet Explorerが普及し始めた時代です。本HPを開設した2006年も、今ほどネット検索が当たり前ではなく、私は図書館の大きく分厚い辞典・字典をめくりながら、文字の有無や字源を調べていました。
現在、私は、その手間を惜しんで「IMEパッド」や「漢字検索サイト」等で有無を確認しています。もちろん、この方法が不完全であることは言うまでもありません。しかし、私の作品制作において、文字が既に存在するかどうかは本質ではなく、むしろ、日本で普通に暮らしていて目にすることがほぼない、記憶にすら残らない「(漢字のような)文字」を創り、それにふさわしい造形・線質で表すことこそが、私のその時々の想いを表現する手段です。
そのため、
契丹文字・
女真文字・
チュノム
などの漢字に影響を受けた文字や、
「同じ形(複数)の組み合わせで構成される漢字」
等を調査することは、当初から諦めていました。
また、以前、漢字に詳しい方のサイトで質問したところ、第1作「自己矛盾(心を上下に重ねる)」は国字として存在していること、そして、文字として存在しないことの証明は不可能、とのご回答をいただきました。さらに、私は研究者でもなければ、字源を極める目的もないことから、白川説・他説等、都合よく取り入れていることも事実で、2007年の「心の鏡」にて「漢字はしばしば複数の意味を持つことを、恥を忍んで言い訳とした」経緯もあります。
さて、私の制作スタイルは、
テーマ・コンセプトの着想
⇒ 創字
⇒ ふさわしい造形・線での揮毫
という流れであるため、全作品に共通する私特有の個性的な特徴(書体・造形・線質 ≒ フォント感)はありません。しかし、可能であれば、一瞥のみで私の作品であるという印象とバラエティ感をもたせた作品、つまり、ともすれば二律背反する目標・方向性を意識して創作してきました。
ネット環境の発展により、30年前と異なり、さまざまな作品が、特定の権威による評価を経ることなく、真に「通りすがりの人」に直接届くようになりました。私は、今後も、過度な謙譲の美徳や、通時的・共時的な束縛・比較から解放された環境で制作し続けたいと思っています。
|