
|
ベクトル | ||
| 文字 | |||
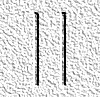
|
|||
| 解説 | |||
|
数学で習う「ベクトル」は、方向を持つ量を表す概念であり、社会一般においても「方向性」を意味する言葉として広く使われる。 数学では、文字の上に右矢印(→)を書いていたが、漢字に置き換えた場合、漢字の部首の「丨」が造形・意味の両面で適していると考えた。 一本の横棒が「一」、二本の横棒が「二」となる。漢字が、単純な造形によって意味を持たせる表意文字であることも踏まえ、「丨」を二本並べることで、 ベクトルの持つ「方向性の概念」および「シンプルな形状による抽象性」を表した。 「丨」は、説文解字によれば、「下から上に書けば進む、上から下に書けば退く」という意味をもつ。 また、「『説文解字』に収録されているものの、字として使われた例がなく、分類のために作字 されたものである」とされる。 実は「中」も「串」も、2024年の「合従連衡・離合集散」で用いた「Y」も「丨」を部首とするが、 漢和辞典でも「丨」がそのまま明示的に偏や旁として構成されている文字は見当たらないため、これも、新たな偏・旁と言えよう。 本作品は、作品集の中でも最も単純で象徴性が高く、創字100文字目という分岐点として、左右の筆致・呼吸・大きさ・紙質等の対比によって、上記説文解字の意味を踏まえ、 過去を振り返りつつ、今後の方向性(ベクトル)の拡張感をイメージした。 |
|||
| トップページ | 作品一覧 | 次の作品 |